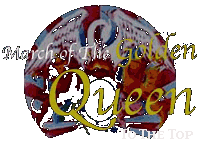
< What did I feel ? >

Queen (1973)
Keep Yourself Alive 2002.01.28 UP
Doing All Right 2002.02.03 UP
Great King Rat 2002.02.11 UP
My Fairy King 2002.02.18 UP
Liar 2002.02.26 UP
The Night Comes Down 2002.03.07 UP
Modern Times Rock'n'Roll 2002.03.15 UP
Son and Daughter 2002.03.29 UP
Jesus 2002.04.10 UP
Seven Seas of Rhye 2002.04.24 UP
← Back
|
Keep Yourself Alive
これが Queen の音源としての記念すべき第1作目です。 左チャンネルから、しかもいきなり一拍目の裏から入るギターに続いて 右チャンネルに現れるギターも半端な拍から、さらにその後に続く「何か」を 叩く音もまるで途中で思いついたかのように半端な所から始まり、ベースは スネアがリズムに参加する時にやっと加わって来ます。 そして3人が演奏に加わったのを確認するかのように Freddie がぼそっと一言。 今まで別々の人生を送って来た4人が初めてここで1つになった、とでも 言いたげに、これから20年という膨大な時間を Queen として過ごす4人の音楽が 始まります。 Brian のギターは手製のオリジナルと言う事ももちろんありますが、ピックの 代わりに6ペンスコインを使っているためにピッキングの瞬間が「ポン」では なく「ジャリッ」と言う感じになって、それが彼のギターの音をより深みのある ものに感じさせてくれます。(私は友人に借りたギターを、父に出張先から 持ち帰ってもらった6ペンスコインで一時期練習していました…) このオープニングでもフェイズのようなエフェクトをかけているようですが、 エフェクト類によるもの以上にコインによってその効果がとてもよく出ています。 叩いていた「何か」は最初ミュートをしたカウベルのようにも聞こえますが、 その後ハイハットが加わって更にはタンバリンを振るような音も重なって来ます。 初期の Roger のドラムは彼の好みでかなり深めの胴の楽器を使用し、チューニング も低めに設定しているようで、特にスネアはとても独特な音色を持っています。 時折入るタムもやはり個性的で、深い響きに加えて低めのチューニングのためか 叩かれたヘッドがたわむのが目に見えるような不思議な立体感を感じさせます。 曲の構成はさほど複雑でなく、と言うより至ってシンプルで、導入からの基本が Amで歌詞が入ってF、そしてサビが6度上のDと言う展開の繰り返しになって いますが、Dのコードに持っていく為のコード進行がとてもスムーズで明るく さわやかな事と、あまり目立ちませんが随所に入るJohn の経過音の飾り付けが この曲を単調に聴かせない大きなポイントになっているような気がします。 コードと言う観点で面白いと思うのがドラムのチューニングです。 中間部のドラムソロでメインに使っている2つのタムのピッチがそれぞれEとBに なっていて、それは即ちコードのないはずのドラムソロの部分をEのコードに 感じさせるのです。 最初チューニングはたまたまなのかと思いましたが、その少し後に登場する 「Do you think you're better everyday?」の部分が同じEである事を考えると 意識されたものである気がしてならず、とても興味深いです。 また、ドラムソロが最後の2拍を除いて全て16分音符の羅列のみ、と言うのも 面白く(34拍間ひたすら136個の16分音符を叩き続けている)アクセントの 位置だけで成立しているソロからは、何か吐き出したいエネルギーをため込んで いるような印象さえ与えられます。 そしてそれが終わった瞬間、キーを半音上のFに上げて繰り広げられる壮大な ギターオーケストレーションによる間奏が「吐き出された」ような素晴らしい 立体感を持って広がって来るのが、予め計算されたドラムソロの上に成り立って いる事が分かってここでまた感動してしまう訳です。 曲全体としては Freddie のオーバーダビングによる畳み掛けるようなボーカルの テンポがとても心地よく、また彼らの今後への意気込みが感じられる作品で、 Queen の曲にあまり好き嫌いはないと思っていますが、この Keep Yourself Alive は とても大好きな曲の1つです。 ↑ Top ← Back |
| Doing All Right 前の Keep Yourself Alive の最後で少々強引とも思えるBへの転調がありますが、 この曲 Doing All Right が始まるとその理由が解ります。 Eのキーであるこの曲へのドミナントとして前述のBを使い、前曲とは全く異なる ニュアンスのこの曲へすんなりと導いてくれる、という訳です。 この曲で特筆すべき事は何と言っても Freddie の歌唱力の凄さです。 1コーラス目の甘く優しい歌声は前曲と同じ喉の持ち主とは思えないくらい全く 違った世界に聴く人を引きずり込んでしまいますが、更に曲の進行と共に彼の 歌声は少しずつ、しかし確実に変化して行きます。 1コーラスを通してベースがEに固定されていますが、これはクラシック音楽では 頻繁に使われる手法で、流れの停滞、混沌とした様子を表す事が多いようです。 メロディーも1つの上昇と下降を3回繰り返しているだけで大きな変化は見られ ませんが、これも停滞を表現するのに一役買っています。 1コーラス目の最後でベースが初めてIV度のAに上がってハッとさせられると 同時にサビである「Doing All Right」のハーモニーが特別に響くのはそうした 停滞からの開放感が大きく作用しているようです。 2コーラス目の前からは今までシンバルでの飾りのみだったドラムがリズムを 刻み出し、ギターは積極的に飾りを入れ出しますが、ここでも凄いと思うのが やはり歌唱力です。 2コーラス目でバックの楽器を増やすという構成は色々なジャンルの音楽で かなり古くから好んで用いられた方法ですが、同じメロディーを1コーラス目 とは明らかに違う声色(こわいろ)で朗々と歌い上げる Freddie、冒頭では 昨日今日の事を、ここでは明日の事を思っていると言う物語の「展開」を声の 質だけで見事に表現していて、この時点ですでにゾクゾクさせられてしまいます。 上がったAをドミナントとしてDに転調した3コーラス目ではギターのみの伴奏 となりますが、今度はDのコードに留まらず sun、skies という大きな物の登場 と共にコード進行も動きを持ち始めます。 Freddie の歌には絶妙なバランスで息の音が入り、ギターの伴奏と共に何とも 言えない煌びやかな雰囲気を醸し出しています。 そして There ain't time in all the world のくだりではB♭→A→B♭→Aと言う 不安定な進行を使って絶望感を表しているのがよく解ります。 4コーラス目は間奏への橋渡し的な位置を占めていますが、ここでの Freddie は前の息の混ざった声を捨て、激しい間奏へ向けて声の質をどんどん張りの ある太いものへと変化させて行きます。 こんなに場面場面で声色を的確に使い分けられるボーカリストがロック界で他に いるでしょうか? ギターの間奏では最初の8小節はベースの動きがE→B→D→Aと目まぐるしく 変わりますが9小節目以降はまたしてもEに固定され、ワンコードでのソロに 続いてそのまま2コーラス目と同じ形の5コーラス目になだれ込みます。 ここでの Freddie は2コーラス目と同じ声で歌っていますが、自分のすべき事を 知っているのが「I」から「God」へと変わっている所など、ちょっとした事が たまらなくニクイと感じてしまいます。 曲全体を通して楽器やコードの使い方に留まらずボーカルの歌唱力、表現力と 歌詞とが密接に関わり合いながら進んで行く音楽はイタリアオペラに通じる物が あり、30年近くも前にこんな力を持ったボーカリストがロック界に存在した事は 凄い事だと思いますし、またこの先にも彼のような逸材は現れて来ないのかも 知れません。 ↑ Top ← Back |
| Great King Rat 前曲のEを受け継いで少々こもった、しかし異様に太い音色のギターで Freddie の Queen としての初お披露目であるこの曲は始まります。 ドラムの短い乱打の後すぐに始まるリズムからはコード進行(Am→G→E→Am) と共にフラメンコを連想させられますが、この幻想的で重々しい歌詞は何を 題材にした物なのでしょう、何かに戦いを挑むような凛々しい歌いっぷりの Freddie はとにかくカッコイイの一言に尽きます。 バックではアコースティック・ギターでフラメンコのリズムが常に刻まれ、 ドラムは凄味の効いた深胴のスネアで迫り来るようなリズムをキープ、たまに 入るタムがスネアの響き線を共鳴させてフィルインを立体的に演出します。 サビの部分では一瞬アコースティック・ギターは消えてスネアのリズムも 8ビートに変わってスケールが広がりますが、直後に加わる小気味良いアゴゴ ベル(大小のカウベルをくっつけたようなもの)とその後の短いコーラスが ほんの8小節のサビを実に色彩豊かに聴かせてくれます。 1コーラス目で時折飾りを入れていたレスペの方は、2コーラス目ではワウの ようなエフェクターを通して徐々に存在感を増して来ますが、間奏に入ると 右チャンネルのワウのかかっていないギターとのバトルに展開して行きます。 サビの部分を含めてまるまる2コーラス分のサイズで展開されるバトルですが ここがこの曲の最大の聴き所の1つではないでしょうか。とにかくカッコイイ! サビを1つ挟んで展開部へと入って行きますが、凛々しい Freddie の声には 残響が増されて更に伸びのある艶やかな声へと変化します。 Queen の作品には後にも Freddie が大衆の前に出て物を諭すような場面の歌詞 が度々登場しますが、ここではその堂々とした様子がタムのリズムと音色で とても良く表現されていると同時に、コードが長いDとAのみに固定された事 でそれまでの動から静へ、しかも不動の静と言う「確固たる物」のイメージが 見事に表現されています。 展開部の2コーラス目の前には sinners が足に繋がれた鎖を引きずっているよう な効果音が聞こえますが、この描写の細かさはまるでミュージカルかオペラの それのようで、とても立体的に音楽を楽しむ事が出来ます。 突然フラメンコのリズムが戻って来た後にはキーをCmに変えて再び長いギター ソロが始まり、Brian のセンスを充分に堪能する事が出来ます。 短い拍手(なぜここで?)の後に続く後半、左チャンネルで最初の4小節を2本 の弦でEの音1つを弾ききり、後半4小節でF#→G→Aと音を上げて途中から参加 した右チャンネルの Freddie の歌う(ずっとギターの音だと思っていました!) Aに向かって行くだけのソロなのですが、これが何かを訴えて叫んでいるような 迫力を持って迫って来るのがまたたまらなく、やはり最大の聴き所の1つだと 思っています。 サビを1つ挟んで念を押すように歌詞を変えて物語は終わって行きますが、音楽 はそこで終結せずAmの4度であるDのコードを鳴らしたまま、今度は次のコーラス に入らずにスネアの乱打でフェイドアウトして行きます。 この形は楽典上では半終止に分類され、知りたくない?見たい?と問われたまま 曲が終わって行く事で消化不良的な感覚を持たされるエンディングはこの半終止 によって的確に描かれているのではないでしょうか。 曲の構成としてはそれほど複雑でないものの、Freddie の凛々しいボーカルと 音楽の描写力、そして Brian のギターソロのセンスが抜群に光る、とにかく カッコイイ1曲です。 ↑ Top ← Back |
| My Fairy King 冒頭のギターは皆さんにはどう聞こえますか?「うっ」?「ぷっ」? いずれにしてもよくこんなに単音のみでありながら印象的なオープニングを 思いつくものだと感心せずにはいられません。 4分音符を正確に刻むハイハットに乗るギターは、怪しげなスケールと共に 微妙にヨレた不思議なリズムで徐々に緊張感をあおって来ます。 参加したピアノは典型的な60'sロックのリズムなのですが、途中でキーが 2度上がる事と、驚異的でいて尚かつ華麗な Roger の声によってそのリズム からは不思議と全く古臭さが感じられません。 それどころか個人的に私は何百回これを聴いても Roger の圧倒的な声に鳥肌 を立ててしまい、そして体中の血液の温度が上がって行くような感覚に陥って しまいます。 この曲はいわゆるロック、もっと大きな意味でポップス音楽に欠かせない要素 の1つである1コーラス、2コーラスという形式の概念から一歩踏み出した、 Freddie がとても自由で柔軟な、そして大胆で斬新なアイディアの持ち主であった 事がはかり知れる作品の1つだと思います。 大きく6つの部分に分けられるこの曲には場面が展開した後同じメロディーが 使われる事が二度となく、6つの場面場面で次々と新しい音楽が放出されます。 この神秘的な世界を情景描写している最初の部分では、まず1つのフレーズが 3小節単位になっていて直後にはごく自然に変拍子も挿入されて、割り切れる 通常からかけ離れた世界である事が技法的に、しかもさりげなく表現されてい ます。 ここでの Freddie のボーカルがファルセットを用いているのも聴く人を神秘の 世界に誘うのに一役買っているのではないでしょうか。 ギターによる美しい間奏に続く部分では Fairy King に思いを巡らせますが、 ファルセットと実声を微妙に織り交ぜたボーカルに複雑に絡み付くコーラスが Fairy King が実体のない抽象的な存在である事を示すかのように、やはり聴く 人を神秘の世界に導いてくれます。 そして何かに反発するような高らかな叫びに乗って舞台はおどろおどろしい 場面へと展開して行きます。 これまで John の美しいベースラインに乗って目まぐるしく、そして華やかに 変化して来たコードはここではAmとDmに固定されていて、更に複雑化する のではなく2コードに固定する事によって場面が展開している事を表現する所 など、これぞ Queen!と言う感じがします。 物語は再び情景描写に入りますが、冒頭の静かで穏やかな物とは違って内容 も邪悪な物へと変化して行き、情景にも動きが加わって来ます。 コード進行、メロディーライン共に徐々に上昇して行く事でこの状況がただ 事ではないと言う緊迫感が的確に描かれていてドキドキされられます。 短い間奏では冒頭の60'sロックのリズムが早めのテンポで現れ、ギターの 参入によって更にテンションが上がって来た所で突然の静寂が訪れます。 悲しい結末を嘆くように波打つテンポのピアノに乗って歌われる Freddie の歌からはやはり彼の抜群のセンスが見て取れて、彼の世界に引きずり込 まれてしまいそうになります。 後奏を1つの部分とするならばここが6つ目の部分と言う事になります。 ここではまず行く先の見えない不安感をあおる上昇型のメロディーがギター によって繰り広げられますが、完璧主義の Freddie にしては珍しくピアノに 大きなミスタッチがあるままこのテイクを採用しています。 ついついこれにも何か意味があるのではと勘ぐってしまうのですが…。 このギターのフレーズは後に A Day At The Races の象徴のようなメロディー として扱われる事になりますが、輪廻を思わせるようなこの不思議な音の 鎖にどんな意味が含まれているのか、とても興味のある所です。 単に後奏と言ってしまうにはあまりにもドラマティックな後奏はピアノと ギターによって最高潮まで盛り上げられますが、ここでまた突然訪れる 静寂に続くギターが何とも悲しげにロマンティックに響き、曲はやはり 解決されないDの音を残して終わって行きます。 昔レコードで Queen を聴いていた頃は、素晴らしい映画を観た後すぐに 映画館を出ずに暫くはそこに座ったまま余韻を楽しみたくなるようにこの 曲、そしてこの面が終わると何だかすぐには盤面をB面に返す事が出来な かったのですが、CDになってからは否応なしにすぐ次の Liar が始まって しまうのが少々残念な気がします。 ↑ Top ← Back |
| Liar 冒頭の3+3+3+3+2+2と言うリズムはロックに限らずごく一般的に頻繁に 使われるリズム(次作 Queen II の Ogre Battle にも登場する)ですが、これ が前曲 My Fairy King の歌の冒頭と弱起こそないものの同じであると言うのは 単なる偶然でしょうか。 エフェクタのかかったドラムのリズムに続いて始まる序曲のような前奏は 40小節と言う長さで前半をA、後半をEのコードに固定していますが、コード に動きのないまま形が少しずつ変化して行く事で次への展開への欲求が徐々 に増されて行って、最後に突然Dに解決した時には急に視界が開けたような驚 きと安堵感を与えられます。 静かなアコースティック・ギターのアルペジオに乗って淡々と自分の罪を 省みる所に突然叩きつけるようなスネア、続いて彼を卑下するような叫び声、 ますます罪の意識に苛まれ追いつめられて行くと言う状況、感情の変化が ストレートに表現されています。 22小節間Aに固定された間奏では周囲の非難の声が増大して緊張感が高まる ようなギターソロが展開され、続くサビではコーラスとボーカルのテンポの 良い掛け合いが繰り広げられます。 Freddie の表現力は勿論ですが、コーラスに重なった力強く荒々しい Roger の叫びにも似た声なくしてはこの部分の緊迫感はあり得ず、彼らの歌唱力を 最大限に活かした見事なアレンジに恐れ入ってしまいます。 これまであまり動きのなかったコード進行ですが、ここに来て初めて1小節 ごとにコードが変化し始めます。 ここで歌われるのは、許しを請い助けを求めると言ういわば「すがる」思い を表した物ですが、コードに初めて動きが与えられた事と Freddie の声の質 が見事に切り替えられている事でこの曲の中で最も印象的な部分の1つに感 じられます。 続くギターソロ、前半では同じフレーズをオーバーダビングしているよう ですが、チョーキングの度合いを微妙に変えてピッチのずれを生じさせる事 で気持ちのうねりを表しているようにも聞こえます。 後半では後の Brighton Rock にも見られるI→IV→I→IVの進行の繰り返しが 印象的で、にわかに熱くなったギターによって流れはそのまま次の展開部へ と突入します。 高鳴る鼓動にも似たバスドラム、冒頭にも使われたアゴゴベルのような楽器 のリズム、そして微かに聞こえるコンガ(これが実に効果的に使われている) に乗って激しい口調で忠誠を誓い祈り始めるこの部分はやはりとても印象的 で、挿入されるギターのリフ(これも Brighton Rock の最後の部分で同じもの が聞かれる)とも相まって激しい心の動きが的確に表されています。 テンションの高いクリアなベースの動きに導かれて悟ったような安堵感が訪 れた後には延々続いたEのコードを打ち消すようにDが明るく鳴り響きますが、 実は訪れたのは安堵感ではなく絶望感だった事に気付かされ、ステージ映え する「かっこいい」ロックの形を取りながら主人公の心の動きを実に巧みに、 そしてドラマティックに表現したこの秀作にはとても奥の深い物を感じざる を得ません。 ↑ Top ← Back |
| The Night Comes Down 前曲に続いて長い前奏を伴うこの曲ですが、おどろおどろしい前奏や後奏に 対して歌詞を伴う部分は実に簡潔に整理されていて、その対比がこの曲を より一層印象深い物にしている気がします。 闇を裂くように打ち抜かれるドラムの音色はかつてない程の印象的な音色に チューニングされていて、1曲ごとにドラムのチューニングを変えると言う Roger のこだわりが感じられます。 またピッキングノイズを極端に取り入れたアコースティック・ギターが奏 でるメロディーは4分の1拍早く始まっていて、次の小節でちょうど1拍目 から入るベースと4分の1拍ずれたまま進行して行くなど、混沌を表現する ために緻密な計算がされている事から当時の彼らがプログレッシブ・ロック を少なからず継承している事がうかがえます。 ドラムが4ビートを刻み出すと混沌は一旦整理されますが、Emの9thである F#の音に固執したまま更に緊張感が高められて行き、やがてそれはドラマ ティックなブレイクによって断ち切られ、ティンパニーを思わせるような ドラムのリズムに続いて開離のコード(それぞれの声部の音域が遠く離れた 和音の重ね方)で重ねられたギターがクラシカルに印象的に響きます。 4分音符でビートを刻むギターと音域を広く使った美しいベースラインに 乗って歌われる Freddie の声はとても甘く艶っぽく、実声とファルセットを 交互に巧みに使い分けるテクニックも見られ、多少ピッチを外しながらも 美しいフレーズを朗々と歌い上げます。 続くサビの部分では透明感のあるコーラスとさりげなく入るギター・オーケ ストレーションによる合いの手が「サビは4度のコードから」と言うセオリー による物以上にこの部分を爽やかに開放的に聴かせてくれます。 2コーラス目では先ほどよりも4小節早くドラムが加わりますが、その参加の 仕方がこの部分の雰囲気に反して大袈裟で自己主張が感じられ、それにつら れるかのように後半ではベースラインも自己主張を強め、個人的にはとても 楽しく聴ける部分の1つです。 このコーラスの最後の部分でGmaj7→B♭と言う長調でありながら短調のよう な効果をもたらすコード進行が用いられていますが、メロディーの中でこの 効果を左右する音であるFナチュラルが、1コーラス目のこの部分では一瞬使 われた後すぐにF#が来る事でそれ程短調が登場した効果がはっきりとは現れ ていませんが、この2コーラス目ではそのFナチュラルが付点8分音符と言う 比較的長い時間使われ、しかもその後二度とF#に戻る事がなく短調の性格が はっきりと前面に押し出されています。 これは即ち1コーラス目では過去の明るさを、そして2コーラス目では現在の 暗さを、と言う相対する内容を歌った物を表現する手段として使われていて、 ここでもロックの域を超えた彼らの音楽性を楽しむ事が出来ると思います。 続くサビが終わると前奏と同じ形を取った、しかし今度はギターの持続音に よって緊張感をあおって行く後奏が延々と混沌を表し、それは再びドラマ ティックなブレイクによって中断されて、次のハードロック・ナンバーへと 実に巧みに受け渡されて行きます。 混沌と爽やかさ、明るさと暗さ、(歌詞にも a black and the white と出て来 ますが)この曲の中には相対する2つの物が凝縮され実に簡潔に整理されて いて、この曲が後の Queen II の Side White と Side Black と言う概念を生み 出したのではないか、と思ってしまうのは考え過ぎでしょうか。 ↑ Top ← Back |
| Modern Times Rock'n'Roll ロックンロールはこう!と言わんばかりの Roger の初めての作品は、前曲 の激しいブレークを受けて冒頭からハイテンションで始まります。 この曲が高いテンションを保ち続けているのは Roger のボーカルのテンポ の良さによる所はもちろん、ドラムに徹底してクローズ・ハイハットを 使わない事がまず挙げられます。 3度のブレークを除いて4分音符を全てオープン・ハイハットとクラッシュ・ シンバルで刻む事によってこの曲の「騒々しさ」は見事に保たれています。 構成は至ってシンプルで、コードも基本的にはI・IV・Vのスリーコードのみ で進行するのですが、この曲に変化をもたらしているのはボーカルのリズム です。 やたらと歌詞をまくし立てるのではなく、それぞれのアップテンポで始まっ たフレーズは2回に1回程少し緩んだリズムで収められ、スピード感溢れる 中にも大きな前後への動きが盛り込まれているのは流石です。 また3コーラス全てに渡ってきちんと韻が踏まれているのも大きな特徴で、 Roger が歌詞の「音」に持つこだわりが強く感じられるのも楽しいです。 オープン・ハイハットの4分音符で刻まれ続けた1コーラス目は突然のクロー ズ・ハイハットによってブレークを迎えますが、そこに一瞬聞こえるギター のフィードバックのような音がさりげなく、しかし実に効果的に使われてい て益々この曲をかっこよく聴かせてくれます。 同じスタイルでブレークを迎える2コーラス目ですが、ここではブレークの 直後に見事なまでに8分音符に収められた非常にテンポのよい歌詞がここま での最高音を越える音域で荒々しく歌われ、続くサビの部分では逆に最も 長い音でコーラスが入ると言う実にメリハリの利いた構成になっています。 ここまで徹底してオープン・ハイハットを使って来ましたが、このコーラス が登場するとその後のギターソロの部分を含めて4分音符はクラッシュ・シ ンバルによって刻まれる事になります。 通常ならこう言う部分で使うであろうライド・シンバルを使わずに敢えて クラッシュのみを使用している事で「騒々しさ」は誇張され、ギターソロは 否が応にも盛り上がります。 ギターソロが終わると同時にピアノがグリッサンドで印象的に登場し、その 後ピアノは3コーラス目では細かい8分音符や2拍3連のような大きなリズム でバッキングに参加しますが、これが Freddie の唯一(?)の自己主張なの でしょうか、この3コーラス目をとても幅広いイメージに作り上げるのに一 役買っています。 Emを基本として来たこの曲は、Queen のメンバー以外(Baker氏?)の一声 によって平行調であるGに変わり、明るいコーラスとエコーを伴った Roger の叫びによって突然印象的なエンディングを迎えます。 彼の若々しさとロックンロール・スピリットが痛いほど伝わって来るとても 大好きな曲なのですが、これが若さと勢いにまかせたばかりのものでなく しっかりと構成が計算されている事には唸らされてしまいます。 ↑ Top ← Back |
| Son and Daughter この曲がこのアルバムの中である意味最も「シンプル」な曲かも知れません。 構成的にはエンディングの部分を除いて2つの形しか持っておらず、場面の 展開もキーの大きな転調もなく、ギターソロさえもありません。 それなのになぜかこの曲が自分の中では印象的に位置づけられています。 Brian のハードロック志向の一部が大変良く表れているこの曲の大きな特徴 の1つは7thの音使いにこだわっている所でしょう。 冒頭のコーラスがいきなりEm7で、しかも7thの音を金属的な Roger の声で 一番上に持って来るのに始まって、ギターとユニゾンで動くベースラインも 最高音に7thを使用しています。 5度上のBにコードを移した後は更に5度上のF#、3度上のAと2小節ずつ コードが変わって行きますが、ここのF#とAの部分でもボーカルに効果的に 7thの音を取り入れていて、曲全体に於いて重たい7thのニュアンスを前面に 押し出しているのが大きな特徴になっています。 その「重たさ」を強調しているのが Roger のドラミングです。 先日発売された QUEEN FILE の中で西脇氏も触れていましたが、Roger 独特 のハイハットのクローズのタイミングによってアクセントの部分、即ちスネ アの入る部分に時折一定の長さが与えられて「単調なノリからはみ出す」 かっこよさを味わう事が出来ます。 コードの面では前曲と同様に長調と短調の同居、つまりギターのEmajorに コーラスのEm7が乗る、と言う手法を用いている事も付け加えておかなけれ ばならないでしょう。 そしてこの曲が紛れもなく Queen の音に仕上がっているのは、Brian 独特の ギター・オーケストレーションの素晴らしさによる所に他なりません。 2コーラス目の中間部とエンディングに突然現れる美しい音の重なりは オーロラのような天体現象をも思わせる、シンセサイザーにも出せないよう な幻想的な色彩感を持ってこの曲に味付けをする事に成功しています。 突然テンポを変えるエンディングには多少無理矢理の感もありますが、この 思い立ったような疾走が次の曲の冒頭のBmを更に重たく、堂々と聴かせるの に一役買っているのかも知れません。 一見単調な曲ですが、コード・リズム・装飾と色々な所に彼らならではの 工夫が凝らされていてやはり印象に残ってしまう1曲です。 ↑ Top ← Back |
| Jesus クラシックで頻繁に使われるmaestoso(=荘厳に)、risoluto(=決然と)と 言う曲想用語がこれほどしっくり来るロックも珍しいかも知れません。 アルバムを通して聴くとLiar以来の Freddie の曲ですが、彼のボーカルは 口の動きが目に浮かぶ程のはっきりとした発音で正に荘厳に、そして決然と この曲を歌い切っていて、後のBarcelonaの圧倒的な歌唱力の基礎がこの 時期にかなり出来上がっていたと思われる程の見事な熱唱となっています。 そして何と言ってもこの曲の最も大きな特徴はリズムの独特さに他ならない でしょう。 冒頭では一瞬この曲が2拍目から始まっているようにも聞こえますが、実は これは1拍目から始まる音楽で、最強拍が常に4拍目に来ています。 その最強拍はドラムの3連符によって表されていますが、ギターとベース、 そしてシンバルではこの最強拍がドラムとは違う3拍目に来ています。 更にボーカルに至っては主に2拍目に最強拍が来るフレージングを取って いて、これもドラムともギターとも違うと言う訳です。 このような最強拍のずれによって2コードの単調な筈の音楽は推進力を与え られて荘厳に、それでいて躍動的に前進して行きます。 そしてコーラスが入るサビの部分では、今まで1拍づつずれていた最強拍が 一気に4拍目の裏に集結し、テーマを連呼するのに相応しいトータル感が たまらない快感を伴って押し寄せて来ます。 これまで「カッチリ」と歌っていた Freddie がサビの部分で自由に動き出す のもコーラスと共に開放感を演出していて気持ちよく聴く事が出来ます。 3コーラス目ではこれまでBmだったキーを半音上のCmに上げますが、転調 前の最後のコード、Gのソプラノ声部であるDの音を転調後のCmのE♭に上昇 する音として使っている為に違和感なく転調が行われています。 サビではまたもとのキーに戻りますが、ここでもCmの5度であるGのコード を転調後のDmajorの4度に置き換えてそこからIV→V→Iとスムーズに転調を 完了させているのも見事です。 間奏の途中からは古くからジャズ等で用いられて来た「ダブル・テンポ」 が使われています。 一見何の脈絡もないテンポの変化のようですが、ここでの新しいテンポは これまでのテンポの丁度倍になっていて、もとのテンポに戻った時に何の 違和感もなく再び荘厳な再現部に身をゆだねる事が出来ます。 ダブル・テンポの部分が8分の6拍子と早い4分の3拍子の複合リズムである 事も面白く、プログレッシブを匂わせるこの部分でこのアルバムがデビュー アルバムであった事を再認識させられるような気もします。 あまりディストーションの効いていない、弦のニュアンスを充分に楽しむ 事の出来るギターも心地よく、複雑に絡み合ったオーバーダビングも良く バランスの取れたアンサンブルとして実にかっこよく聴く事が出来ます。 「決然と」速弾きされるギターに誘導されてラスト・コーラスを迎えます が、このサビの部分ではコーラスを残して楽器の伴奏が徐々にフェイド アウトして行き、残されたコーラスの最後の1小節にはかなり深めのエコー がかけられて美しいエンディングを迎えます。 荘厳に、決然と終わるのではなく、続く架空の土地の物語への序章にこの 曲を繋げて行きたいと言う、彼らがこのアルバムでこだわって来た物を ここでも強く感じる事が出来ます。 ↑ Top ← Back |
| Seven Seas of Rhye ファーストアルバムの最後を飾るこの曲は Queen、特に Freddie がこだわっ た曲間の関連性、連続性をアルバム単位でもこだわって見せた最初の作品 になります。 本編であるセカンドアルバムの同名の曲よりも落ち着いたテンポで、ピアノ の音域を始め全体のテンションも低めに押さえられていて、聴いていると メンバーがこの曲をBGMに、静かにこんな風に語りかけて来るような気が します。 「僕たちのファーストアルバムは如何でしたか?僕たちはこのアルバムを 1つの長大な作品としてお楽しみ頂けたんじゃないかと思います。それ ぞれの個性は強い4人ですが運命的に出会ったこの4つの個性を調和させ てこんなアルバムを作ってみました。僕たちの世界はまだまだ続きます。 どうぞこの後発表される次のアルバムを楽しみにしていて下さい。では それまでの間しばしのお別れです…」 My Fairy Kingの感想でも書きましたが、まるで映画を1本見終わった後の ような余韻を楽しめるA面・B面です。さらにこの曲では Queen の世界に 40分弱の時間身をゆだねて、現実の世界に引き戻される前に彼ら自身に よる「次回予告」を聴かせてもらっているような1分強を体験する事が出 来ます。 曲はピアノのアルペジオに続いてギターとベースが加わってDとGを基本と したコードの繰り返しと言うイントロですが、前の曲がDのキーの3度で あるF#で半終止しているのにここはV→IのBではなく同じ主調のDで始めて いる事から、前からの続きではなくまさしく「予告編」的な性格をこの曲 に持たせている事が分かります。 イントロが終わると少々テンポを上げて、高い音域を使ったベースに乗って Brian がオーバーダビングで色々な表情を見せてくれます。エフェクターの 種類の違いもさる事ながら、ほんの短い時間ですが他の曲同様に彼の様々な フレーズのほんの端々を披露されて、フェイドアウトと共に次作への期待を 盛り上げてくれて行っています。 このアルバムを荒削りだと言う声も多いようですが、彼らはこのファースト アルバムで紛れもなく自分たちのやりたい事をやって行く為の基礎を完成さ せているように思います。 後の彼らの作品と比較され未熟だと見られがちですが、他の何にも例えられ ない、Queenでしかないこの作品は音楽的要素やセンス、レコーディングの 技術や熱意、どれをとっても実に洗練されているのではないでしょうか。 これだけの作品を完成させての「次回予告」、彼らには相当の次作への自信 があったに違いありません。映画はこれで完結せず、物語は次作へと続いて 行きます。ファーストアルバムはこれから続く本当に長大な世界へのほんの プロローグなのかも知れません。 ちなみにDのままフェイドアウトするこの曲ですが、Queen II の冒頭はV→Iの 法則に基づいてやはりGmでの幕開けとなります…。 ↑ Top ← Back |
[ 注 ]
私は楽器のハード面などについては大した知識を持っていません。
Queen の使用する楽器等について詳しい知識をお持ちの方が読んで
見当外れな文章があるかも知れませんがご容赦下さい。
また、正しくない事については正しい情報を頂ければ幸いです。
← Back
このページのTopへ