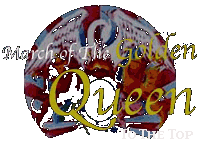
< What did I feel ? >

Queen II (1974)
Procession 2002.05.06 UP
Father to Son 2002.06.23 UP
White Queen 2002.07.10 UP
Some Day One Day 2002.11.15 UP
The Loser in The End 2002.12.28 UP
Ogre Battle 2003.02.03 UP
The Fairy Feller's Master-Stroke 2004.05.12 UP
Nevermore 2004.05.31 UP
← Back
| Procession 静かに脈打つ鼓動のように響きを押さえられたバスドラムに続いて、左チャ ンネルからいきなり Brian のギター・オーケストレーションの世界が繰り広 げられ、セカンドアルバム「Queen II」の幕が開けられます。 音色がエレキ・ギターであると言う事以外、これから始まるのがロックの アルバムである事は全く想像がつきません。まるで弦楽四重奏のような高貴 さ溢れる曲想と対位法からは、Queen がこのアルバムで確立している神秘的 な世界の幕開けをこの曲が象徴している事をうかがい知る事が出来ます。 冒頭から保たれている鼓動は4拍目から開始されているようですが、全体に 拍子をあまり感じさせずにアンサンブルに重点の置かれたアレンジに気品が 漂います。 右チャンネルに最初に現れるギターはチェロをイメージしているのではない かと思われますが、ここで Brian は各音をピッキングした直後に落としてい たヴォリュームのつまみをその都度上げて行く事で音の立ち上がりを弦楽器 に似せる奏法を用いていて、それは見事に弦楽合奏的な効果を上げています。 また最低音のDはアームを使って音程を下げる事によって出しているようで すが、これも重々しくも高貴な雰囲気を醸し出すのに一役買っています。 2フレーズ目では主旋律が右チャンネルに移動し、それまでアンサンブル対 ベースラインと言う対比を各チャンネルで取って来ましたが、ここからは 高音域アンサンブル対低音域アンサンブルと言う、ルネッサンスの頃より 受け継がれている器楽・声楽法であるChoir(コア)の概念が取り入れられて ますます優雅に、そして豪華にオーケストレーションは彩られて行きます。 冒頭の4分音符・付点8分音符・16分音符・2分音符と言うリズムですが、 あくまで個人的な想像の域を出ないのですが、これは Father to Son と言う 言葉からのモチーフであるような気がします。 王が多くのしもべを従えてゆっくりと入場して来る様子を描いたような この曲ですが、最後の3連符ではっきりと次の曲である Father to Son の メロディーが使われている事から、王、つまり父が息子へ王位の継承を する様子が表現されている描写音楽であるように聞こえてなりません。 ともあれ、これから繰り広げられるドラマティックな Queen の世界に浸る ときめきは、脈打つ鼓動と共に徐々に高揚して行きます。 ↑ Top ← Back |
| Father to Son 前曲の最後に聞かれるシンセサイザー的な効果のギターは前曲のドミナント からコードが解決した後、ハードロック調のギターが登場してG→F→E♭→ Dと進行して行く間もアルペジオと共に鳴り続き、8分音符のタムに誘われ て現れるCのコードの出現と共に姿を消し、ここまで続いた展開部からあっ と言う間に更なる展開部へとその姿を変えて行きます。 伸びのあるボーカルが参加すると、ここまでコードを押さえて弾いて来た ギターは単音のオーバーダビングによるコードへと姿を変え、イントロの ハードロック調とはまた違った豪華さ・高貴さを醸し出しています。 一瞬はっとさせられるEのコードに印象的なスネアのロールが絡み、短い サビの部分ではコード弾きに戻ったギターにコーラスが乗りますが、ここ でのコーラスの音使いが面白く、ボーカル部とコーラスの最高声部の関係 が全く同等である事が不思議な効果を演出しているようで印象的です。 2コーラス目では単音のオーバーダビングによるギターは伴奏に留まらずに 広い音域をフルに使ったギター・オーケストレーションへと発展して音の 広がりを広大な物へと導いて行ってくれます。 これから物を告げると言う厳粛な場面である1コーラス目から一転、告げら れるその内容の大きさや深さ、そして尊さのスケールがギター・オーケスト レーションによって表現されているあたりはさすが Biran の作品、と言わざ るを得ません。 2度目のサビが終わると再びシンセサイザー的な効果のギターが顔を出しま すが、今度はハードロック調のギターもドラムも登場せずに、ベースのみで 冒頭と同じ下降進行が演奏され、そのためかシンセ効果のギターがここでは 更に神秘的に響いて来ます。 構成上の真の展開部である次の部分では唐突にFのキーに転調した後コードも 暫くFに固定されますが、左チャンネルで3回繰り返される下降型のコーラス と右チャンネルで常に上昇を続けるコーラスの絡みは鳥肌が立つくらい見事 で、たまらなくかっこいいベースの「おかず」と相まって、信じられない程 絶妙な緊迫感を伴ったアンサンブルとして完成されています。 続いて現れる突然のA♭には驚かされますが、このコードは次のEのキーの3度 であるG#としても同時に扱われ、たったの4小節ですがこの曲中最もドラマ ティックなコーラスを伴ってハードロック部へと突入して行きます。 ハードロックと言えばEかAと言われますが、ここからは暫くEのキーに固定さ れる事になり、声質をハードロック調に変化させたボーカルに続いて Brian の長いギターソロが始まります。 ドラムとE→D→Cの進行によって一旦一息つくように間を置いた後再びギター ソロが再開されますが、主に左チャンネルで弾かれるソロに対して右チャン ネルではフレーズの一部を時折ディレイを使うような効果で追いかけている のが楽しい部分です。 そして同じように一息つくと思いきや唐突に現れるフリーテンポのバラード、 ピアノ伴奏と囁くようなボーカルにはっとさせられるや否や、深めの残響と 更なる声質の変化を伴って場面はすぐに次へと展開して行きます。 3コーラス目になるのでしょうか、この部分ではバックにコーラスの持続音 が加わる事で以前とは違う、何かを悟ってしまったような落ち着きのような 物さえ感じられ、続くハーフテンポの部分ではアコースティック・ギターを 伴って Freddie の効果的なファルセットによる「想い」を聴く事が出来ます。 前曲の最後に使われた上昇型がそのままコーラスで再現されてコーダ部へと 入りますが、ここでは音色を変えたギターのアドリブ、コードを弾くアコー スティック・ギター、オクターブで歌われるメロディー、と様々な新要素が 登場して楽しませてくれます。 そしてフェイドアウトと共に現れる開離和音の持続音は次第にその姿をはっ きりさせて行き、またしてもそのまま次の曲へと受け継がれて行く事になり ます。 展開の早さと華麗さ、ドラマティックな構成、コード進行の意外性、Freddie の「巧さ」等々、アルバムの最初からこれ程までに贅沢な技を披露されてし まってはもうこのアルバムにはまって行かない訳には行きません。 オペラ座と並んで初期 Queen の最高傑作とされる事の多いこのアルバムには 彼らのそうしたエッセンスが充分過ぎる程詰まっています。 ↑ Top ← Back |
| White Queen (As It Began) 前曲から受け継がれたバイオリンのような音色の開離和音のギターによって キーはGからDへと導かれ、アコースティック・ギターの登場でDに落ち着い たような錯覚に一旦陥ります。 しかしここからのG→D→Emと言う進行からはトニックがDではない事が伺い 知れ、これこそがこの曲を神秘的に演出している「技」なのでしょう、例え ようのない独特な世界に聴く者を引きずり込んでしまいます。 解決するEmがトニックであると言うよりも、ここでは中世の教会旋法である ドリアン・スケールをベースとしたような、ロックの世界に於いては間違い なく異色と言える色彩感を持った音使いを披露してくれています。 またこの部分のビートも特徴的で、あたかも毎回弱起に感じられるフレーズ の冒頭は実は全て1拍目に位置する物で、今後このフレーズが登場する度に ここへの入りと出の都度、変拍子を伴ったような錯覚に陥る仕掛けになって いるのは大変興味深い事です。 そしてマレットによるシンバルとアコースティック・ギターのみの伴奏で歌 われる絶望的な哀しみに満ちた歌によって、これから語られる物語の中にい つの間にか導かれてしまうのです。 ベースとエレキ・ギターが加わり、コード進行自体はAm→Am/G→F7→Eと 言うごく普通のAmのキーでの進行に変わりますが、アルペジオでのF7に於 けるDとE♭の使い方やEのコードでAを使ってsus4として扱うなど、これでも かと言うくらい効果的で美しい音が散りばめられています。 1コーラス目、旋律は非和声音であるBの音からの形を繰り返し、進行して 行くコードについて行く事なく漂い、ここでもマレットで奏されるシンバル とタム、そして途中から現れるバスドラムによって更に混沌とした様子が描 かれています。 美しいコーラスが登場すると共に事態は動きを見せ、急速に「動」の方向に 向かって行きますが、後半のD→Am→D→Aに乗ったコーラスは実に劇的で、 最後のAのコードに含まれるC♯が宇宙的な広大さを持って明るく響き渡ると 音楽は更に激しさを増して行きます。 ギターにはディストーションがかかりドラムには初めてスティックが使われ Freddie の声質も見事に力強い物に切り替えられているこの部分ですが、こ れがハードロックになっていないのはやはり冒頭同様、メロディの音使いに 教会旋法の香りが漂う為でしょう、壮大に男性的に、しかし悲観的に歌われ る7小節はすぐにその勢いを失って2コーラス目へと入って行きます。 2コーラス目ではマレットによるタムの装飾が所狭しと駆け巡り、状況を語 るに留まっていた1コーラス目に対してここでは著しく揺れ動く心が描写さ れているようです。 そして続く展開して行く部分では、前回Amから始まって力強さを増して行っ たのとは異なり、A→Dm→F7と言う印象的な進行に続いてロマン派のオペラ のようなドラマティックな悲壮感を持って混沌としたインストゥルメンタル 部に突入します。 通常音楽を聴く時に、人は一度提示されたメロディを記憶して二度目にそれ が現れた時には当然一度目の記憶を元にその進行を予測する物だと思います が、曲名である「White Queen」が歌詞に登場するたった二度の部分をその 最も大きな「予測を裏切る」箇所に選ぶなど、どうすれば自分の音楽をより ドラマティックに聴かせる事が出来るかを理論上知り尽くした Brian なら ではのこの上ないテクニックが使われ、見事に感動させられてしまいます。 シタールの音色を模した何とも悲しげなギターソロが延々と続き、現在なら 間違いなくシンセサイザーで作るような神秘的な持続音のコーラスが絶妙な バランスでうっすらと保たれ、出口のない哀しみの中をさまようような効果 を演出しています。 再びハードにG→D→Emが現れるとこの曲中初めてドラムにスネアが登場し ギターのオーバーダビングによる弦楽合奏的なコーラスをバックに「泣きの ギター」がエアロスミス張りに奏されますが、Gm7→E7sus4→E7と移り行 く進行が恐ろしく劇的に響き、右チャンネルに現れるピッキングを伴った ギター・オーケストレーションには何度聴いても鳥肌が立ってしまいます。 ボーカルが入るとバックはコーラスとギター・オーケストレーションが重 ねられた重厚で力強い響きへと発展し、再びD→Am→D→Aを介して冒頭の 静けさへと還って行きます。 そして再びマレットによるシンバルとアコースティック・ギターのみの伴 奏となり、過去にも未来にも絶望して光の見えないまま物語は静かに終わ りを告げます。 この後数年間に及ぶ Queen のドラマティックな音楽構成には、ここで開花 した Brian の音楽的な知識と恐ろしいほどのセンスによる物が大きく影響 している事、そしてこの曲が彼の傑作の1つである事は間違いないでしょう。 時間にして4分半程の曲ですが、それに気付いた時の感覚は仮眠の間に壮大 な夢を見たような感じにも似て、自分の感じた時間と実際に流れた時間との あまりのギャップに驚いたものです。 ↑ Top ← Back |
| Some Day One Day Brian が初めてリード・ボーカルを取る事になるこの曲は、後のアルバムに 続くShe Makes Me、'39、少し飛んで Leaving Home Ain't Easy と同様にほぼ アコースティック・ギターを中心に音が作られ、それが彼の少し頼りなげで 不安定な声質と妙にマッチしていると言う大きな特徴があります。 彼の声に混ざる「シャリシャリ」とした摩擦音のようなノイズからは一種の 儚さのような物さえ感じられて、それがアコースティック・ギターの弦が擦 られる音と不思議な一体感を生み出しているのかも知れません。 この曲で特筆すべきは何と言ってもメロディーに執拗に7thの音を使っている 点で、9小節目から参加するギターのメロディーでいきなりコードのAに対し ての7thであるGの音を使い、それがボーカルの前半8小節でも引き続き執拗 に姿を見せ続けています。 これは状態が不安定なまま持続している事を和声的に示していて、このメロ ディーの8小節間が「先に進みたいのにそれが出来ない」と言うようなもどか しさを感じさせ、フェイザーのようなエフェクターを通して複雑に絡み合う バックのギターコードも「持続」「停滞」を表すのに一役買っています。 欲しかった物を散々じらされた挙げ句に与えられるように表れる9小節目の ギターは5度とオクターブを重ねた重々しい響きを伴って上昇を始め、突然 Aのコードから解放される事も手伝って否が応にもハッとさせられます。 しかもこの部分の4小節目で初めてAのキーの音階音であるG♯がメロディー に使われて、聴く者は「今まで何かに縛られていたけれど今はその何かから 解放された」ような安堵感とこれからへの希望を感じる事が出来て、そして それが彼がこの曲で言わんとするテーマ「希望」であるだろう事は言うまで もありません。 サビらしいサビを持たないこの曲が妙に印象に残るのも、この停滞と解放を 3コーラス分ただ淡々と繰り返される事によって無意識のうちに「希望」の 感覚を植え付けられてしまうせいなのかも知れません。 2コーラス目も構成は全く同じですが、導入部でG音を使ってメロディアス に登場するベースがその後の2コーラス目でも引き続き滑るような美しい ベースラインを奏でているのが目を引く所です。 2コーラス目の最後では、1コーラス目の最後には聞かれなかった深いリバ ーブを伴ったコーラスが被って来るのも印象的で、再び表れるメロディアス なベースラインに先導されて間奏部分へと突入して行きます。 間奏は自由に滑るベースに乗って左チャンネルの低音ソロ、右チャンネルの 高音ソロが実に見事に絡み合い、延々とコードを持続する絶妙なバランスの コーラスが何とも言えない広がりを演出しています。 3コーラス目に入っても右チャンネルの高音ソロが4小節被って来ているの が面白く、また2コーラス目の後半ではギター・オーケストレーションに よる物だったバックが3コーラス目ではコーラスに取って代わられ、コーラス の最後には歌詞が付いているなど細かい効果まで変化を持たせる工夫をして いて深い所まで楽しませてくれます。 後奏の部分では、遅れて入って来る右チャンネルのソロの直前にスイッチか シールドのような電気的なノイズが聞かれますが、意図的にこれを入れたか どうかは別にして「いざ出陣!」的な爽快感をこのノイズによって感じてし まうのは私だけでしょうか。 その後もこのソロが全体をリードし続け、後奏の後半では左チャンネルで ギター・オーケストレーションとも違った実に複雑に絡み合った音の群が 右チャンネルに対抗して所狭しとひしめき合いながらフェイドアウトして 行きます。 前曲の White Queen のような壮大でドラマティックな大作に対して、この 曲はシンプルな構成でテーマをはっきりさせる中に複雑な要素を組み込む事 で彼のサウンドに仕上げてしまっていますが、Side White のここまでの彼の 4作品には当時持っていた彼の音楽的センス、才能を全て注ぎ込んだ事を痛 感せずにはいられず、ため息の出る思いで聴き終えるのです。 ↑ Top ← Back |
| The Loser in The End 重々しく、そして叩きつけるようなドラムがこれまでの美しい透明感を持っ た流れを遮断するともうここからは一転して Roger の世界、思い切り低く チューニングしたドラムがパワフルに響いて、彼の大きく見開いた目と飛び 散る汗が目に浮かんで来るようです。 変拍子のような錯覚を伴うドラムのみのリズムからはまだ調性感は見えて来 ませんが唐突に、しかも不気味にも聞こえるマリンバのE-G#-Eが実はこの 曲のトニックであるAmを導き出すドミナントとして機能しています。 彼の声はしゃがれているばかりでなく実に多くの倍音を含んでいて、渋み・ 深み・華やかさを兼ね備えた独特な声質は、前作の Modern Times〜よりも ここでは更にその個性を発揮しているように思います。 上でトニックはAmだと書きましたが、確かにメロディーとベースラインには マイナーの3音であるCが使われているもののバックのギターは最も重さを表 すのに適するAとEの5度のみを使っている為に、性格上沈んだ感じが暫く続い て後のDのコードを印象づけるのにも一役買っています。 そして再び顔を出すマリンバのE-G#-EがこのAmの上に乗っていますが、こ れがAmMaj7ではなくAmとEが同時に響いているような錯覚を与え、イントロ のドラムに乗ったマリンバが不気味に聞こえた理由がここではっきりするの かも知れません。 またこれ程ヘヴィな音楽のバックにアコースティックギターを絡めると言う 発想も斬新で、この辺りにも Queen ならではの音作りのアイディアが見られて 楽しめます。 そして、続くDのコードをはっきりと印象づけてくれているのがハモンドオル ガンのような大きく波打つキーボードの持続音、Amの部分から左チャンネル で活躍していたアコースティックギターと重なってDの3音であるF#をはっき りと認識させられます。 曲のタイトルにもしている重要な歌詞を2度繰り返している訳ですが、冒頭 からこの1度目までをずっと同じコードで一貫して来て、2度目の時に初めて 4度上のコードに展開する、しかもその部分で初めてキーボードをかぶせて いるなどの工夫が見えて来るのも楽しい所です。 最も言いたい事を連呼する、2度目は1度目よりも高揚する、これはクラシッ ク音楽でも頻繁に用いられる手法ですが、ここでの連呼はそれに通ずる物が あるのかも知れません。 コードは続いてA、そしてGへと展開しますがここでのトニックがAmではなく はっきりとAであるのが印象的で、バックのAに乗る Roger の旋律の最高音が CからC#に向かってベンドしている事、そしてGのコードでは同じ部分が7th のFからF#に向かってベンドしている事によってそれぞれが中間音に聞こえ る為にどちらともつかない独特なニュアンスを醸し出しています。 右チャンネルのギターもここまで合いの手役で活躍して来ていますが、使っ ているフレーズはシンプルであるもののエフェクタによって固く荒々しい 音色を作っていて、途切れ途切れに喘ぐような音使いは正に Roger がここで 言わんとする「嘆き」を的確に表現しています。 2コーラス目も構成は1コーラス目と同じですが、"Goodbye Ma"と出て行く 息子の閉めるドアの音がしたり、マリンバの音が G#-E-G#と反転していた りとちょっとした遊び心も忘れずに取り込んでいるようです。 短いギターソロと重々しいタムのソロが一発のスネアで締められると、一時 的にトニックを4度上のDとするD-G-D-Gのサビに入りますが、続くD-G-C -Aと言う印象的な進行の部分にこのサビで最も彼が伝えたいであろう辛い メッセージを充てているのは見事です。 ここでもAのコードの部分でCからC#へのベンドが聞かれますが、暗めの Amに一度落ち着く要素と続くDへのドミナントとしてのAと言う要素の2つ を兼ね備えたAのコードなのかも知れません。 D-G-C-Dと最後だけを変えてD→3コーラス目のAmへと戻って行くと、もう 語り尽くしてしまったと言うかのようにそこはすでにコーラスの後半、その まま後奏へと突入して行きます。 後奏での進行はAmとGのみでギターは荒々しく吠え、ベースとドラムはお互 いを刺激し合いながら高揚して行きそのままフェイドアウトして行きますが ここでの各楽器の絡み方はプログレッシブ・ロックの片鱗を充分に思わせる 熱っぽさを感じさせてくれます。 Roger のストレートな感情表現そのままのヘヴィ・サウンドと至ってシンプ ルな構成を持つこの曲ですが、泥臭さを感じさせない音使いと彼の声質によ る華やかさ、そして彼の内面が垣間見えるような内容の歌詞、徹底して韻を 踏む遊び心などが際立つ大好きな1曲です。 ストレートに心に響く Side White をこのヘヴィな1曲で締めくくった後は、 ブラックコーヒーでも飲みながらミステリアスな Freddie の世界に足を踏み 入れる心の準備をしたいものです。 ↑ Top ← Back |
| Ogre Battle 誰の追随をも許さない Freddie 独特の世界への導入は、とことん人と違った 事を好む彼らしく実に創造性豊かに幕を開けます。 冒頭部分、平穏な世界に迫り来る邪悪な鬼を取り巻く暗雲の到来はシンセサ イザーのようにも聞こえますが、これは銅鑼の音が逆回転された物で、イン トロの途中まではこの曲の最後8小節ほどがそのまま逆回転で使われている と言う何ともユニークなアイデアが用いられています。 銅鑼に続いて最高音にGを持つ衝撃的なEmのコーラスが突如耳を刺しますが、 続くAのコードのコーラスでは最高音がEであるはずがここではなぜかC#が 強く出ている為に、Em→Aの進行が最高音に於いて減5度(G→C#)の下降と 言う最も緊張感、不安感を煽るメロディ進行を結果的に導いています。 この減5度進行は日本では歩行者用信号機の青色点滅の音によく使われる 進行で、この音の発案者はこの進行の効果を知った上で横断中の歩行者に その効果を期待したのではないかと思われますが、果たしてこの曲に於いて Freddie がそれを意識していたのかどうかは定かでありません。 ギター、ベース、ドラム、コーラスの全てが逆回転なので通常の奏法では得 られない独特のおどろおどろしさがありますが、前アルバムの Liar の冒頭に も使われた3+3+3+3+2+2のリズムでAmのコードに落ち着いた後の3小節 目からは、逆回転でない通常の方法での演奏に切り替えられています。 このリズムは本来逆回転した場合全く別のリズムになってしまいますが、強 拍を感じさせるタイミングをずらす事によって1拍目と4拍目が若干違うリズ ムになるに留める事に成功していて、通常の奏法に戻った時に違和感を与え ないのは見事としか言いようがありません。 キーはここでAmに落ち着いたかのように見えますが、続くコーラスによって 突然A→Dに展開、そして不思議な1拍の間を取った後ボーカルが登場する本来 のキーであるGに落ち着きます。 冒頭のEmからA(m)→D→Gとここに至るまで徹底してV→Iの進行が展開され ている事になり、前奏と呼ぶべきこの部分だけで既に音楽になっているとも 言えるようなこのドラマティックでミステリアスな展開は、彼の持つ最大の 音楽的な魅力の1つと言ってもいいかも知れません。 ボーカルが入りキーがGになると曲調は明るくなったように感じられますが このキーのIII→VIであるBm→Emと言う少々不安定な進行を繰り返し使う事 によって陰の部分を保ち、恐ろしい物への警戒を促す詞を乗せるには巧みと 言えるコードに Freddie の朗々としたボーカルが絶妙なバランスを持って 乗るのが気持ちの良い所です。 Amを基本とするサビでは最高音にCを使ってマイナーである事が強調されま すが、最後にはイントロからボーカルへの橋渡しと同様にD→Gと2回のV→I の進行によってメジャーコードに引き戻されて2コーラス目へと繋がります。 2コーラス目の冒頭ではギターが効果的な低音を出していますがこの音域は エフェクタによる物でしょうか、深くディストーションのかけられた低音が それまでの音量とは明らかに違う大きさで割り込んで来るのがとても気持ち よく感じられます。 1度目のサビではコーラスの最後のコードの構成音が上からD、A、F#と聞 こえますが2度目の同じ部分ではなぜか更に一番下にDを強く聴く事が出来、 これが彼の意図する所であるかは別にして、1度目のメジャーコードに戻る 時とは違ってこの重みのあるDから再びマイナーコードへ、と言う方向性が このコーラスのコード1つから見えて来るのが不思議な所です。 間奏はイントロの後半と同じ形ですがここで3+3+3+3+2+2のリズムが 本当に1拍目からの物なのかと言う疑問が湧いて来ます。 間奏に入る1小節前は1拍足りない3拍子に、間奏の終わりは1拍多い5拍子 になっていて、この事からこのリズム自体が4拍目から始まっていると言う 可能性もある訳で、イントロの不思議な1拍の間もこのために感じられるの かも知れず、拍をずらす事でリズムを複雑に聞かせるプログレッシブ・ロッ クの特徴が活かされていると考える事が出来ます。 ドラムの4つの6連符に続いての展開部は一転してコード進行が滞り、6小節 のAと6小節のBに続いての間奏と言えるのでしょうか、鬼の闘いのシーンで あるDに固定され Steven Tyler 張りの Freddie の雄叫びとギターの効果音に よって劇音楽のように仕上げられているこの部分も印象的です。 間奏明けは突然短調であるAmに展開して先程のAの部分のメロディを基本と しながら2小節が進みますが、続くDm→FonC→Bdim7→E→Amと言う進行で はベースラインの流れの美しさとメロディの持つ説得力に鳥肌が立ってしま います。 このメロディのF→E→D→G#→Aと言うクラシカルな音使いはとてもロック の物とは思えず、意表を突いた展開を見せると共に、一旦終わったこの邪悪 な闘いが永遠に続く物である事への嘆きを高らかに歌うにはこの上ない物で ある事は間違いなく、この4分程の曲の中で最も強く印象に残る部分です。 後奏の3小節目、ドラムが加わってからの部分は前奏の逆回転で使われた物 ですが、後奏のキーであるAmは再び続くコーラスによって突然Aに、そして 今度は前奏のDとは違い関係の薄いEmに飛躍して銅鑼によって締めくくられ ます。 このA→Emの進行がとてつもない緊迫感を醸し出しているのと同時に、Emは 次の曲のキーへの橋渡しの意味も兼ねている事になり、始まったばかりの Freddie の世界がこれから更に奥深くまで展開される事への期待のような物も このエンディングから感じる事が出来ます。 コーラスの Roger の声質効果にも大きく力を得て聴く者を神話の世界へと引 きずり込むのに充分な技法を散りばめた Side Black の1曲目は、正に Freddie が渾身の力と情熱を込めて完成させた名曲の一つと言ってもいいのではない でしょうか。 ↑ Top ← Back |
| The Fairy Feller's Master-Stroke 場面は一転、ミュートギターによると思われる右から左への刻みとハープシ コードによって時空をさかのぼるかのように絵画の妖精の世界へと転換して 行きます。 前曲から受け継いだEmはドラムの参加と共にDへと移行しますが、サイレン ホイッスルや自転車のベル等が刻み続けるハープシコードと相まってこのD のコードを視界が開けたような明るさに感じさせてくれます。 Freddie が意識したかどうかは定かでありませんが、この冒頭のEmは最終 的にボーカル部でAmに落ち着く事になり、G#音からA音と言う導音→主音 の関係は保たれていないものの、進行としてはやはりV→Iの関係にあると 言って良いでしょう。 多重録音のギターによって前奏部分は集結へと向かいますが、本編のAmに 向かうここでの進行がベースのD音からC→GonB→Amと移行していて、また ギターの最高音もE→D→Cと同じく下降している為にAmへの解決が時空の 移動を終え妖精の世界に「着地した」ような感覚をもたらしてくれる気も します。 また4拍子の中に突然現れる2拍子、そして多重録音のギターが現れるCの コードの直前に4拍子からはみ出した8分音符が1つ分挟まると言う不思議な リズムから毎拍に強拍を伴う8ビートのドラムパターンに落ち着いている事 もこの「着地感」を際立たせるのに一役買っています。 この曲は同名の絵画から得たインスピレーションを音楽にした作品ですが、 そこに描かれている登場人物の多さ、多彩さ、煩雑さを表現しているのが 随所に散りばめられたコーラス、効果的に使われるハープシコード、そして 何より目まぐるしく変わって行くコードと、毎拍に強拍を伴うビートに絡む ようにシンコペーションのリズムに乗って華麗に動き回るベースです。 ボーカルの冒頭、前作の1曲目 Keep Yourself Alive にも見られた畳みかける ような別テイクの応酬でまずは絵画全体の煩雑さを表現し、個々の登場人物 の描写ではボーカルの音域をを超えない範囲でコーラスが彩りを添え、一際 目立つ Roger の金切り声を伴うコーラスをきっかけに妖精の描写に入ると コーラスの音域を上げている辺りもその効果が周到に計算されています。 ボーカルの入る部分は基本をAmとしていますが、いくつものコード進行を経 ていつの間にか冒頭のキーであるEmに戻っていて、リズムパターンの変わる 展開部では一旦Cへ(ここでも「着地」で使ったコード進行が現れる)、そし てそれもすぐにFへと展開してしまい、ついにはDmへ落ち着いています。 落ち着く先の見えない目まぐるしいコード進行を楽しむかのようにその間を 縫いながら駆け巡って行くベースの何と心地よい事か、この絵画に命を吹き 込んで登場人物達をせわしなく、楽しそうに動き回らせているベースがこの 作品を完成させているとも言えるでしょう。 落ち着く先であるかのように見えるその都度のキーが長調だったり短調だっ たり定まらない事からも分かるように、この曲そのものが長調なのか短調な のかすら見えにくく、またその事によって多彩さ、煩雑さが見事に表現され ている訳ですからこの手法は見事としか言いようがありません。 上記の展開部に入る直前に現れるユニゾンでのF→GはここではIV→V→Iに従っ てCのキーに進行しますが、次に現れる同じ部分では同じ終止形でも IV→V→ VI、つまりAmに進行して元の着地点に戻った所でドラムパターンの再現と共 に間奏に入る事から、基本的には正統な構成が保たれている事が分かります。 間奏に入るとAmとB♭mがそれぞれ4小節ずつ続きますが、前半Amの部分で はコーラスの最高音が直前のF#から短2度上昇して7thであるG音に向かう事、 そして後半B♭mではA→G♭と言う不安定な増2度進行が執拗に使われている 事でこの8小節間の「短調感」が強調されています。 続いてD→Aの進行が3回繰り返されますが、ここで特筆すべきなのがベース ラインとコーラスは明らかに長調であるのに対してギターソロがDの部分で Dmのスケールを弾いている事で、キーの長短を攪乱する為に煩雑な進行を 用いて来た挙げ句、ついに長短が一体化してしまうこの部分はこの曲の中 でも最も印象的な部分の一つになっています。 間奏の最後はD→C→Bを経てEmに進行すると思いきやそのままAmにスライ ドしていますが、Bの部分でベースが1拍目の裏のA#音からの半音階をE音 まで上昇させた後にAmに進行している事が密かにV→Iの効果を生んでいて この多少無理のある進行をさほど違和感のない物に聴かせている事も見逃 せません。 再び登場するボーカルは2テイクを重ねてあり、多重録音でコードを鳴らす ギターが上昇して行く為に妖精の「一撃」に期待が高まるような高揚感が 表現されている事からも、この部分が実は冒頭の再現部になっている事に 気づきにくい構成になっていて、間もなく再び4分の2拍子を挟んで音楽は 終結部へと突入します。 その2拍子の部分で登場する右チャンネルのハープシコードは大変印象的で すが、同時に左チャンネルで何か金属の物(カウベルかアゴゴベルでしょう か)を叩いてその効果を上げているのが実に彼ららしい細かいこだわりです。 続く4小節間では恐らく右チャンネルに Freddie のみによるコーラス、一方 の左チャンネルには3人によるコーラスを振り分けているのでしょう、その 為にこの部分に広がりと奥行きが感じられると共に、続く「挨拶を交わそう」 と歌う箇所で Freddie の二声がセンターに定位されている事で人物の動作の 進行をも表現しようとしているのかも知れません。 更に続く8小節間でのメロディアスなベースも実に躍動的で、この曲全般に 渡って見られる John の尋常でないセンスを堪能出来るのは嬉しい限りです。 F→G→Cの進行によって最後はCのキーに一旦落ち着きますが、最初に登場し た同じ部分ではその後Dm→A→Fと進行したのに対してこの部分ではDm→B♭ →Fと言う進行を用いていて、その為に明らかにこれまでとは毛色の違うB♭ のコードがとても心地良く耳に響くと同時に、ついに見る事の出来なかった 「一撃」の場面が聴き手の想像に任されたような余韻を残して鑑賞は終了し、 ごく自然に次の曲へと続いて行きます。 なお最後に一旦落ち着いたCのキーは、ここでもそのまま次の曲のキーである Fへ移行するV→I進行の為のドミナントの役割を持つような気がするのは考え 過ぎでしょうか。 絵画の作者 Richard Dadd はこの作品を描く以前に父親を自らの手で殺めてしま ったそうですが、作品の精神分裂的な煩雑さもそれ故でしょうか、しかしそこ に描かれている煩雑さを含めてそれぞれのキャラクターをも誇張し、それを考 えられるあらゆる手段で表現する事に成功している Freddie、そして Queen の 情熱と感性には感服せざるを得ません。 ↑ Top ← Back |
| Nevermore 前曲と次の The March of The Black Queen に挟まれたこの曲は、凝りに凝っ た多彩な手法や動的要素との対句的効果によって得られる静的印象深さ以上 に、聴く人の心をその場に張り付けてしまうような一種独特の神秘的なニュ アンスを持って響いて来ます。 「絶望感」を歌うには、絶望的な悲愴感を漂わせる音楽にその歌詞を乗せる 方法と逆に神の域に達したような優しく安らかな音楽でそれを表現する方法 のどちらを取っても効果的ですが、この場合後者の手法で歌詞を印象的かつ 信じ難いほど美しく哀しく、そして力強く伝える事に成功しています。 極めてシンプルな構成のこの曲の最大の特徴の一つは、トニックへの進行に ドミナントからのV→I(C→F)を殆ど使わずにサブドミナントからのIV→I (B♭→F)を多用している所にあります。 この進行を変格終止と言いますが、またの名をアーメン終止と言われる事か らも分かるように、教会で歌われる讃美歌の最後に付く「アーメン」の部分 で使われるため神へ向けられた気持ちを象徴する進行として古くから使われ ています。 そしてもう一つの特徴はメロディ・ラインに徹底してそのコードの「第3音」 を使っている事でしょう。 ボーカルの入る部分から前半7小節で各小節の冒頭のコードを追ってみると F→Dm→C→B♭、F→Dm→Amとなっていますが、メロディ・ラインの核を 成している各小節の一つ目の音はそれぞれA→F→E→D、A→F→Cと全てその コードの第3音を使っている事が分かります。 和音に於ける第3音は、その和音の長短と言う性格を決定すると共に根音と 第5音のみによる硬い響きに和音としての「柔らかみ」を与える大切な音な ので、その第3音のみを追って作られたメロディの核であれば当然そのメロ ディは落ち着いた、柔らかみのある物になる訳です。 これら二つの大きな特徴は、この曲全体を支配する神、即ち運命の不動性と それに抵抗しようとする自分の無力さ、切なさを美しく哀しく歌い上げる為 に最も効果的に機能していると言えるのではないでしょうか。 1コーラス目の "Don't send me to the path of nevermore" と歌われる部分 と2コーラス目の同じ部分、そして直後の "When you say you didn't love me anymore" の部分がこの曲中最も力強く歌われる箇所ですが、該当個所では それぞれGとAと言うコードが使われています。 1曲を通じて転調する事のないこの曲では一貫してFのキーに含まれるコード のみを使用していますが、前述のG(属調のドミナント)とA(平行調のドミ ナント)のコードだけがこのキーに含まれない「借用和音」である事によっ て耳を奪われ、シンプルな中にも迫り来る説得力を持たせるべきフレーズを 感動的に聴く事が出来ます。 教会的でシンプルなバックに乗せて落ち着いた柔らかいメロディが悲観的な 詩を歌い、テンポに縛られずに時には力強く悲痛な叫びを上げる、正にオペ ラアリアの王道を地で行ったような古典的な作風が他の凝りに凝ったドラマ チックな曲の中にあって一種独特の光を放ち、Freddie の圧倒的な歌唱力も 手伝ってより一層聴く人の心をその場に張り付けてしまいます。 ↑ Top ← Back |
[ 注 ]
私は楽器のハード面などについては大した知識を持っていません。
Queen の使用する楽器等について詳しい知識をお持ちの方が読んで
見当外れな文章があるかも知れませんがご容赦下さい。
また、正しくない事については正しい情報を頂ければ幸いです。
← Back
このページのTopへ