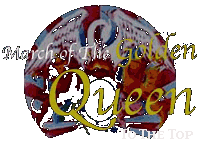
私にとって Queen とは… その2
|
すっかり Queen 漬けになって帰国してみると幾つかの新しい発見がありました。まず驚いたのが MUSIC LIFE 誌に大々的に Queen が取り上げられている事です。Queen を最初に認めたのは日本のファンだと言われていますが、当時はもちろんそんな事は知りませんでしたので「Queen は日本でも有名なんだなぁ」などどただただ喜んだものです。 有名であればさぞや自分の周りにもファンが大勢いるのだろうと思っていたらなぜだか事態は少し違う方向に向かいます。ファンなど周りにはいないのです。MUSIC LIFE 誌には日本のファンの熱狂ぶりがことごとく紹介されているのになぜ自分の周りには Queen を知っている人すら殆どいないのでしょう…? そして、MUSIC LIFE 誌を読んでいると読者からの投稿欄ではファンらしき人達が Freddie を面白おかしくおちょくって遊んでいます。それまで(少しは変な格好だなとか思わなかったでもないですが)神秘的で格好良いと思っていた Freddie がこれだけ遊ばれると、なるほど彼は出っ歯だなぁなどと変に感心したりして少しだけ彼らを身近に感じたりするのでした。 もう1つ、シドニーでは当然 Queen は Queen という文字でしか目に入って来なかったので「クウィーン」と発音していた私は、珍しく Queen を知っていたクラスメイトの書いた「クイーン」の文字を見てとても不思議な感じになったのを良く覚えています。 発音と言えば、テレビを含めてちまたで聞く英語が全てアメリカ英語だと気付いたのもちょうどこの頃でした。私のいたオーストラリアはイギリス英語の「かなり」訛った発音の英語を使うのですが、アメリカ英語にはまた随分違った「くどさ」があるようです。 常々イギリス英語はきれいだなぁと思っていた私は、Queen を聴くようになってからは、特に Brian の発音がとてもイギリス人らしい流れるような美しい英語だと思うようになって、ますます魅力を感じたものです。 そんなこんなで色々な事を感じながら中学1年生の私は日本での「孤独な」Queenファン人生を送り始める事になるのです。 Roger のようなドラマーになりたいという思いもあってか中学では吹奏楽部に入りますが、あいにく打楽器に空きはなく、空いていたトロンボーンに回されてしまいます。それでも Queen を聴くようになって初めて音楽に感動した私は、この楽器で自分もあんなに色々な事を表現して人を感動させる事が出来るかも知れないと思って、縁あって出会ったこのトロンボーンとマジメに付き合っていく決心をするのでした。 しかし家に帰れば部屋にいる時間の殆どを Queen のレコードを聴く事に費やしているのはシドニーにいた頃と変わりありません。この頃には帰国後間もなく買った "Queen" "Queen II" を含めてアルバム4枚分の殆どの曲のドラムパートに合わせて手足が動くようになっていて、ドラムセットなど持ってもいない私は、さも Queen の一員にでもなったかのような気分で、近所の楽器屋で買って来た Ludwig のスティックで相変わらず布団や雑誌をばんばん叩いていました。 そんな中学1年生の冬、部屋で何気なく聴いていたラジオから突然 Queen の名前が聞こえて来たので即座に反応すると、知らない曲が流れて来ます。この頃すでに4枚のアルバム全てが完全に身体に染みついていた私には Freddie の声で Brian のギターで Queen のコーラスで自分の知らない曲が聞こえて来る事に何とも言いようのない不思議な感動を味わってしまいます。 曲名は Somebody To Love、"A Night At The Opera" で限りなく崇高になったQueen の音が更にゴージャスになったような曲で、煌びやかなコーラスに乗るFreddie の艶っぽいボーカルが華麗に駆け巡ります。 ほんの数分間ですが夢の世界に迷い込んだような気分で小さなラジオを見つめているとやがて曲が終わり、DJが言うにはこの曲の入った Queen の新しいアルバムが間もなく発表されるとの事、全身に鳥肌を立たせながら「おぉっ!」などと1人で部屋で歓声を上げるのでした。 間もなく発表されたアルバム "A Day At The Races" ではこれまで感じてきた彼の歌唱力、芸術度の異常とも思える高さを改めて思い知らされる事になり、同時にここまで好きになった芸術家が今現在も自分と同じ(?)地球で活動を続けていてこれからも彼らの新しい作品にどんどん出会って行ける事への喜びが、当時若干13歳になりたての少年をたまらなくワクワクさせてくれたのです。 |
←前へ 次へ→
このページのTopへ